こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
【100均で揃う!道具のポテンシャルを引き出す『製図道具入れ』】

製図道具ってどうやって置いておけばいいの?

使いやすい製図道具入れって何かないの?
と思ってる方にとても参考になると思います!
今日は、別記事の”おすすめ製図道具12選”で紹介した道具のポテンシャルを100%引き出すための『製図道具入れ』についてお話ししていきます!
今日紹介する道具入れはすべて、100均で揃えることができます!

ちなみに、わたしが購入したお店は「Seria」です
製図試験に活躍するおすすめ製図道具については、
こちらで事例付きで詳しく紹介しています!
段ボールBOX(大物の製図道具入れ)

(側面)

(正面)
「大物」の製図道具入れは、
上の写真の「段ボール組み立てBOX」を使いました!

この段ボールBOXに入れる「大物道具」は、次のものです
- 36cmの三角定規
- 勾配定規
- 30cmの三角スケール
- 製図用ブラシ
- 電卓
この段ボールBOXは、”間の仕切りも含めて一つのBOX”に組み上がります!
仕切りが一体的に組みあがるので
「何回か使っているうちに仕切りがズレる」といった心配がありません!
とても使い勝手が良いです!
箱と一体的な仕切りは、ほかにも便利なポイントがあります!
仕切りを持って、邪魔にならないところにすぐ移動できる!
製図道具の「大物」は、作図序盤で役目を終えるものがほとんどです。
ですから、移動しやすさはとっても重要!
床に置くときにも、腰をかがめずに置けるので便利でした!
素材が「段ボール」ということもポイントです!
段ボールなので、乱暴に製図道具入れても衝撃を吸収してくれる
製図道具が傷むと作図効率が下がってしまいます。
特に、三角定規は角が欠けてしまうとかなり使いずらくなります。
衝撃吸収力に優れた段ボールは、かなり良いです!!
ほかにもサイズ感がバッチリなところもおすすめです!
- 定規が絶妙な長さで顔を出してくれる”奥行”
- 箱に”アゴ”があるので、定規やブラシが寝ない
小物立て(小物の製図道具入れ)
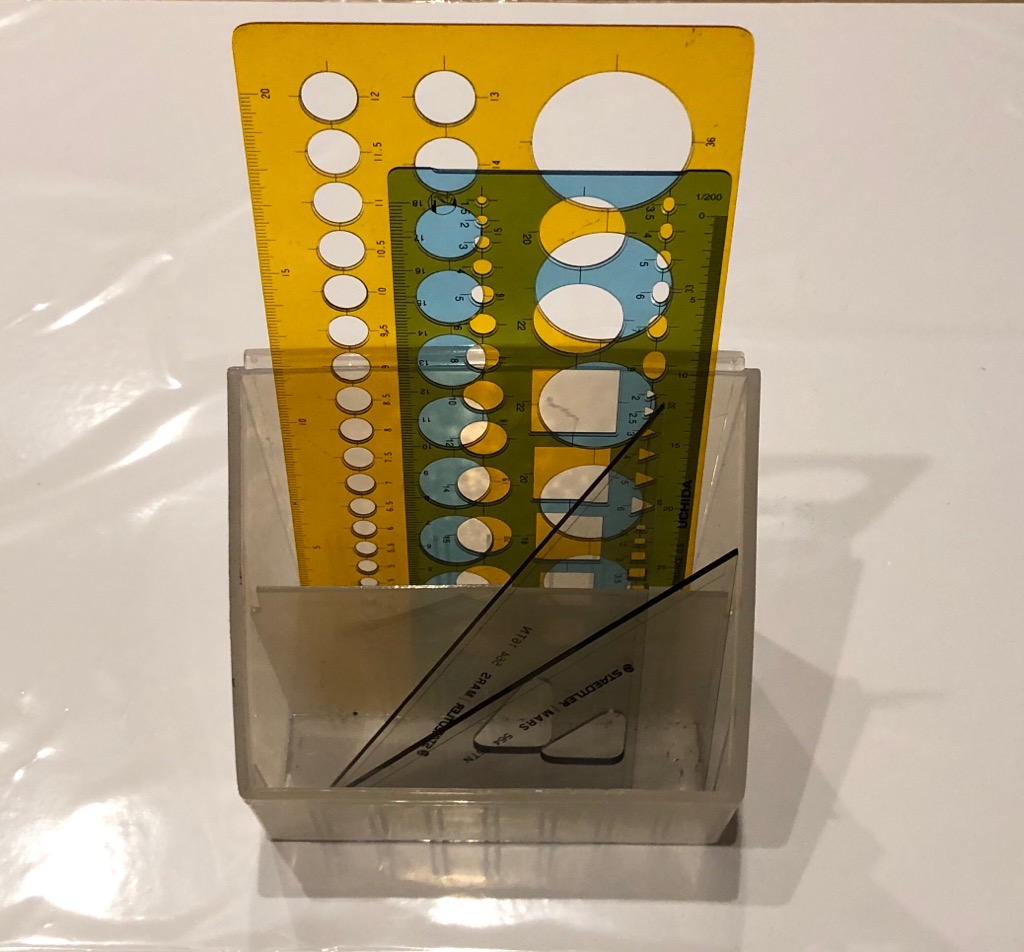

「小物」の製図道具入れは、
上の写真の「半透明なプラスチックの小物立て」を使いました!

この小物立てに入れる「小物」は、次のものです
- 16cm三角定規
- 総合資格学院のテンプレート
- ”丸だけ”のテンプレート
「半透明」というところもポイントです!
半透明なので、視認性が良い!
死角が無くなるので、使いたい道具がすぐ見つかります!
「真ん中の仕切り」も使い勝手向上に役立ちます!
仕切りがあって、利便性向上!
手前に背の低い三角定規、奥に背の高いテンプレートに分けれます!
また、
仕切りがあることで道具もしっかり立ってくれるので、取りやすいです!
テンプレートがちょうど納まるサイズ感もちょうど良いです!
コンパクトなサイズ感で、機動性が優れている!
小物の製図道具は作図中ずっと使うものなので、
取りやすい位置に持ってきたり、
邪魔なときはすぐどかせるなど、
持ち運びしやすい機動性は重要です!
コンパクトでも安定する形状なところも良いです!
斜めにささるペン立て(筆記具や三角スケール入れ)


ペン立ては、「斜めに入れて、4つに分かれてるもの」を選びました!

このペン立てには、次のものを入れてました
- 15cm三角スケール
- マーカー、ペン、4色ボールペン
- 製図用シャープペン
- スティック型消しゴム
「ペンが斜めに刺さる」ことのメリットは大きいです!
- ペンを入れてても、高さが抑えられる
描いてるときに、肘でペン立てを倒しにくい - ペンが取りやすい、戻しやすい
出し入れのときにペン立てを倒すリスクが少ない - ペンが見つけやすい
ペンの全体が見えやすい。
ペン同士が重なっても、前に使っていたものは必ず下になる。
「4つに分かれてる」ことのメリットもあります!
- 取りたいペンを他のペンが邪魔しない!
ペンを分散することで、ペン同士が重なるリスクが激減する! - ペンを見分けやすい
種類ごとに入れる場所を決めて、効率アップ! - 場面に分けたペンの使い分け!
わたしは
奥の3つに「問題文チェックのとき、エスキスのとき、に使うもの」
一番手前側には「作図のとき、に使うもの」しか入れてませんでした!
こうすることで、
終盤にある作図のときに余計な神経を使わなくて済みます!
ペンは持ち替える頻度も多いし、
場面ごとに使うもの・使わないものがあります!
4つに分けれるこのメリットは、けっこう大事です!
”立てれる筆箱”というものがありますが、
- 倒れやすい(倒しやすい)
- ペンがごちゃまぜになって、見つけにくい
- 値段が高い
という理由で、
私としては、おすすめしません!
ふでばこ(シャープペン用と消しゴム用の2つ)

(”シャープペン入れ用”と”消しゴム入れ用”)
最後に「ふでばこ」ですが、これは「筆記具類の持ち運び用」として用意しました!
ですから、製図しているときは使いません!
(中身はすべてペン立てに移し替えます)

私はふでばこを「シャープペンを入れる用」と「消しゴムを入れる用」の2つに分けてました!
- シャープペンに、消しゴムの汚れやカスが付かないようにする
- 消しゴムを、シャープペンが汚したり傷つけたりしないようにする
ちょっと神経質に思われるかも知れませんが、
シャープペンも消しゴムも、製図試験では「超重要な筆記具」と私はおもってます!
ですから、
プラス100円でお互いのベストコンディションに出来るなら、安いものですww
『製図道具入れ』まとめ
今日ご紹介した製図道具入れは次の通りです!
大物の製図道具入れには「段ボール組み立てBOX」を使っていました!

(側面)

(正面)
- 36cmの三角定規
- 勾配定規
- 30cmの三角スケール
- 製図用ブラシ
- 電卓
小物の製図道具入れには「小物立て」を使っていました!
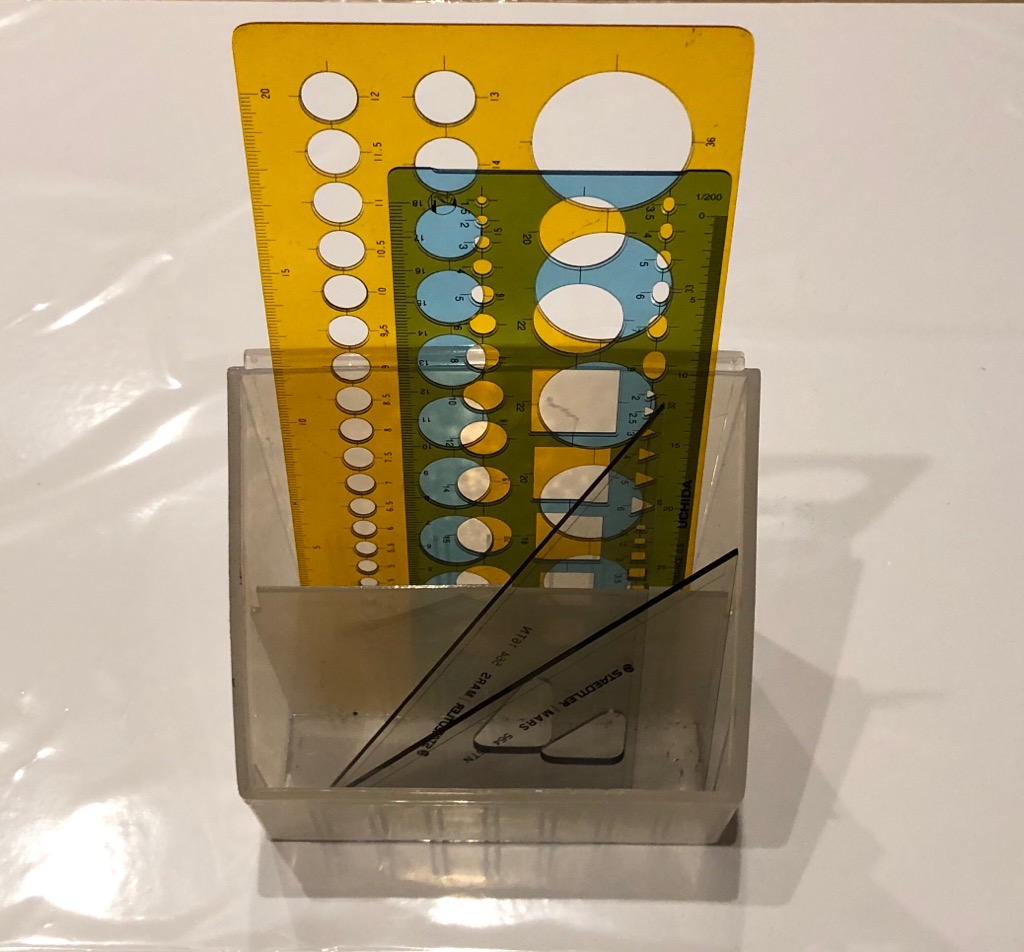

- 16cm三角定規
- 総合資格学院のテンプレート
- ”丸だけ”のテンプレート
筆記具や三角スケール入れには「斜めにささるペン立て」を使っていました!


- 15cm三角スケール
- マーカー、ペン、4色ボールペン
- 製図用シャープペン
- スティック型消しゴム
筆記具類の持ち運び用に「2つの筆箱」を使っていました!

(”シャープペン入れ用”と”消しゴム入れ用”)
- シャープペンに、消しゴムの汚れやカスが付かないようにする
- 消しゴムを、シャープペンが汚したり傷つけたりしないようにする
”製図道具選び”が大事なように、
「製図道具入れ」も自分が使いやすいものにこだわって選んだ方がいいです!
いい道具も、使いにくい環境だとその効果は半減しますからね!
今回紹介したものを一つの参考にしていただけたらうれしいです!
製図試験はスピード勝負!!
「スピードを最大限に活かせる環境」
を作り上げていってください!
頑張ってください!
応援してます!!
最後までお読みいただきありがとうございます!
もしこのブログが
「参考になった」
「わかりやすかった」
とおもっていただけたら、
SNSなどでシェアしていただけると
大変うれしいです!
また、
「勉強していて”ココ”がわからない」
「”コレ”をざっくり解説してほしい」
ということがありましたら
コメント欄でおしえてください!
皆さんとともに
このブログをつくりあげていきたいです!
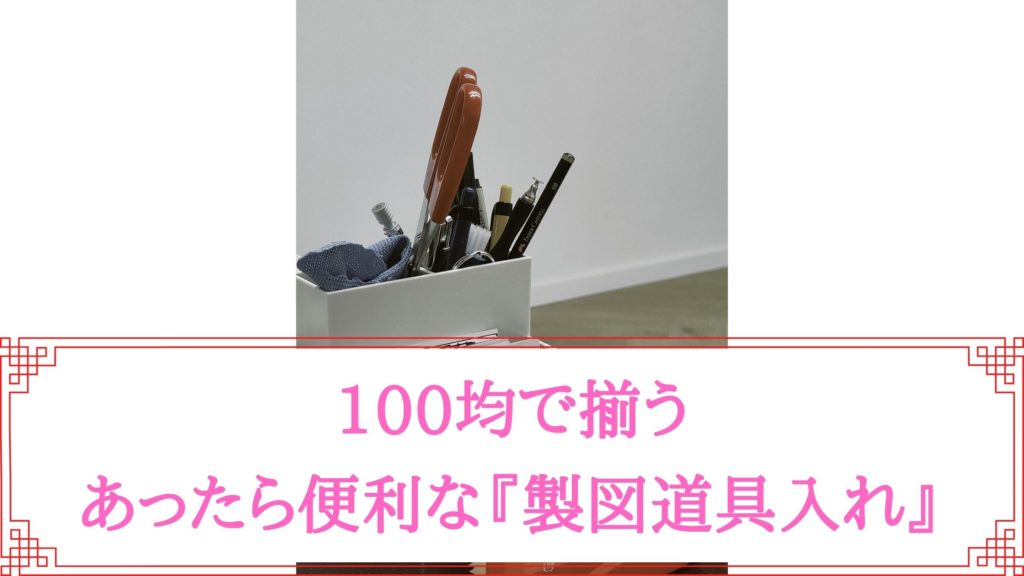
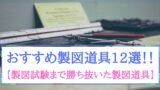
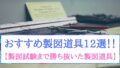

コメント