こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
今日のテーマは
「二級建築士」独学3ヶ月で一発合格した私の勉強法!

二級建築士って独学で取れるの?

おすすめの勉強法があったら知りたい!
二級建築士を独学で目指す人に向けて、私の経験にもとづいて今日はお話ししていきたいとおもいます!
わたしは入社3年目のときに二級建築士を学科・製図の両方とも独学で臨み、一発合格しました!
もともと住宅営業として入社して建築士免許を取るつもりはなかったのですが、3年目でなぜか設計部門に異動になり急に必要になったので取りましたww
「独学で狙える人ってどんな人よ?」
という声もあるかとおもうので、私のスペックをその一例として紹介させていただきます。
- 高校は普通学科
- 大学は建築学科
- 卒業後ハウスメーカーに営業として勤務
- 会社内に二級建築士の製図を教えてくれる物好きな先輩がいた
有名大学というわけではないですが、建築学科卒なのである程度の予備知識はありました。
卒業後は住宅営業になったので、二級建築士試験で中心になる住宅に関わる法律的な知識はひととおり身につけていました。
そしてこれはラッキーでしたが、同じ会社に二級建築士の製図を趣味で教えてくれる先輩がいました。
ある程度の予備知識があって製図を身近に教えてくれる人がいるなら、独学で十分狙える試験です!

「建築の予備知識が無い」「製図を教えてくれる人が身近にいない」
そうした人に向けては、大手学校ではないコスパの良い通信講座を後述しています!
【わたしのイチオシ二級建築士講座】
一級・二級建築士ともストレート合格した経験をもとに様々な通信講座を紹介してきましたが、イチオシの二級建築士講座があります。
それが「ハウジングインテリアカレッジ」です!
ハウジングインテリアカレッジは、20年以上前から二級建築士の製図を指導してきたベテランの資格スクールです!
通信講座でありながら丁寧な製図添削・指導に定評があり、これまで多くの合格者を輩出してきました!
そこに2024年から学科講座も加わったことで、正直二級建築士対策はこれだけで十分じゃないかと思います!
コストパフォーマンスも高く、学科+製図セットの料金を他の講座とまとめたのが次の表です。
| 受講料 (学科+製図セット) | 教育訓練給付制度 | 合格祝い金 | 添削課題 | 質問対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジングインテリアカレッジ | 138,900円 | 対象 (27,780円) ※製図分※ | Amazonギフト券5000円 | 6課題 | 無制限 |
| スタディング | 88,000円 | なし | 1万円 | なし (4課題を自己採点) | 1問につき1,500円~1,000円 |
| 日建学院 | 約61万円 | 対象 (約9万) ※学科分※ | なし | 3課題 | 質問券利用で可能 |
| TAC | 約34万円 | 対象 (約4万円) ※学科分※ | なし | 4課題 | 15回 |
| 建築士会 | 約15万円 | なし | なし | 10課題 | 無制限 |
添削課題や質問対応などのサポート面も含めて考えると、かなりコスパの良い総合講座になります!
ハウジングインテリアカレッジは製図講座が教育訓練給付制度が利用可能なので、条件に合う人は制度を利用してみるとさらにお得に受講することができます!
二級建築士は独学でも取得可能
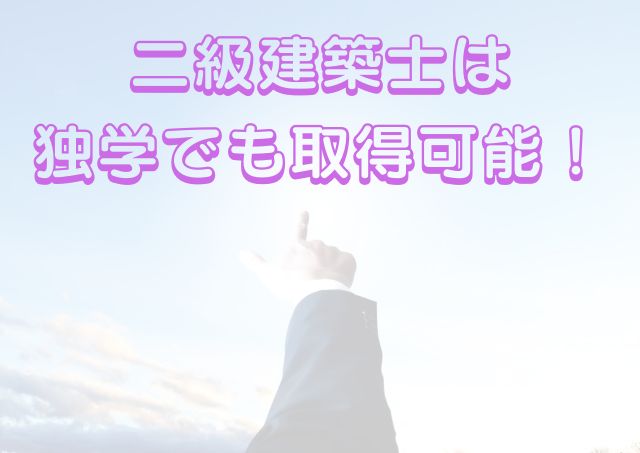
まずはじめに言えることは、二級建築士は独学で十分狙える資格です!
独学で十分狙える理由は、次の2つです!
- 学科でよく出る問題はだいたい決まっている
- 製図は描き上げる力があればたいてい受かる
独学で狙える理由①:学科でよく出る問題はだいたい決まっている
学科は、二級建築士に求められる知識があるかを問われます!
しかし、
二級建築士が建築できる範囲はかなり限定的です!
ですから、必然的に求められる知識の範囲も限定されてきます!
範囲が限定されれば毎年出題される問題も決まってくるため、独学でも対策しやすい試験と言えます!
独学で狙える理由②:製図は描き上げる力があればたいてい受かる
製図試験は、合格率が50%程度と高いです!
しかも受験する人のほとんどが人生初めての製図試験なので、描き上げられずに失格となってしまう人も多いです!
スピーディに描き上げられる手順をマスターして減点になりにくい無難な図面をつくれる力を身につければ、製図試験も独学で十分狙えます!
つまり
製図は描き上げることさえできれば合格できる確率がかなり高くなります!
私が「学科」で用意した教材

二級建築士試験に挑戦する際に最初に立ちはだかる壁が「学科試験」です。
学科試験で出題される問題は、前述したように毎年同じような問題が出題されてきます!
毎年同じような問題が出るので、一番役に立つ参考書はやはり「過去問集」になります!
過去問集は直近5年分
学科はこの過去問集だけで勉強しました!
過去問集は、直近5年分が掲載されているものがオススメです!
学科本試験では直近5年以内に出題された問題が再び登場することがよくあります!
ですから、ここを中心に勉強していくのが一番効率が良いです!

法改正が毎年あるので、最新のものを用意しましょう!
建築士の過去問集の王道と言えば、やはり総合資格が出版している「スーパー7」ですかね!
成美堂出版から出されている過去問集は、解説が別冊になっているので、使い勝手はこっちの方が良いかもです!
用意する法令集はコレ!
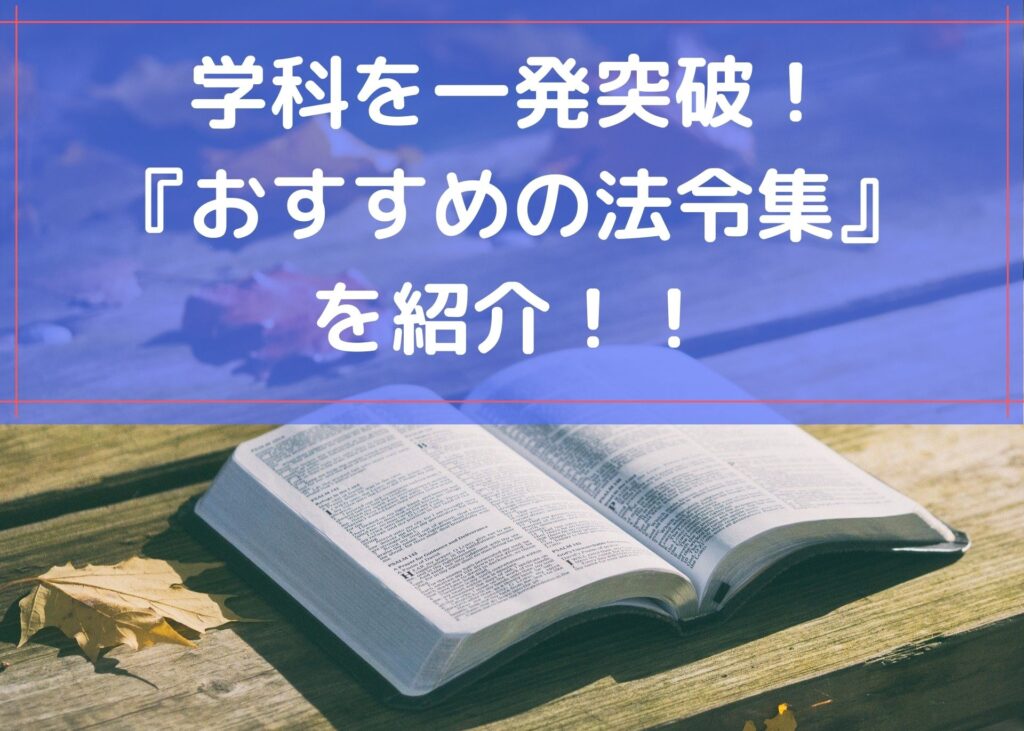
学科試験に法令集は欠かせません!
法改正が毎年あるので、法令集も最新のものを用意しましょう!

私のおすすめ法令集は下の記事で紹介しています!
法令集をまだ用意していない人は、
こちらの記事を参考にしてみてください!
私のこだわり「学科」勉強法

過去問をつかった勉強と聞くと、普通に解いて勉強するように思われるかもしれませんが、そうではありません!
わたしは効率よく勉強することに特にこだわっています!
私のこだわりポイントは次の4つです!
- 問題は解かずに、解説だけ読む
- 正しい設問だけ残して、それも覚える
- ノートは作らず、問題集に直接書き込む
- 1日5分など、無理しない程度に「毎日続ける」
問題は解かずに、解説だけ読む
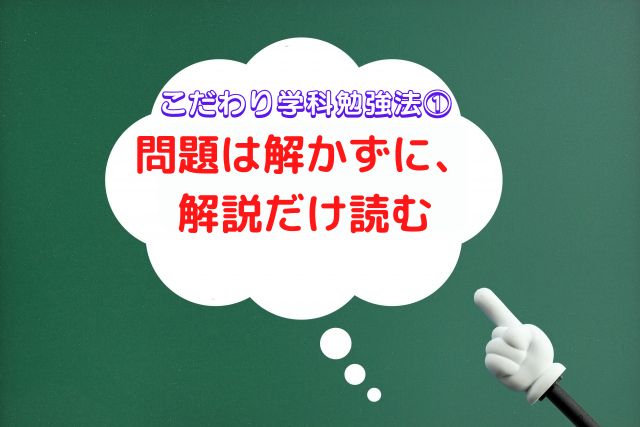
わたしは勉強をするうえで、問題をひたすら解くことに何の意味もないとおもっています!
大事なのは、正しいことを理解することです!
正しいことを理解するためには、解説を読むことが一番です!
「それならテキストを買って読んだ方が・・・」と思う人もいるかも知れませんが、テキストだと過去にどういう問題が出たからその内容が書かれているのか、いまいちよく分かりません!
過去問の解説なら出題された内容も踏まえて覚えることができるので、より実践的な覚え方ができます!

「過去にどういう問題が出題されたか」「その設問で抑えるポイントはどこか」など、問題とリンクさせて覚えることが大切です!
正しい設問だけ残して、それも覚える
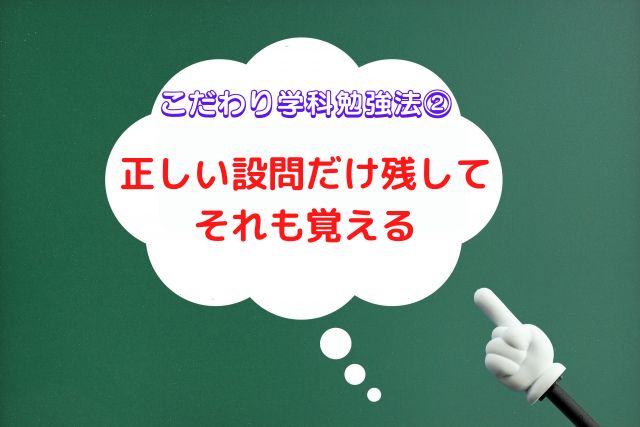
解説の中には「設問と同じ」と書いて説明をはしょってやがるところがあります!
その取りこぼしを防ぐために設問を見に行くのですが、そのときにほかの”誤った記述の設問”も目に入ると毒です!
ですから、
(あらかじめ答えを見ておいて)誤っている設問は黒マーカーなどで完全に消し去っておきます!
例えば、
問題が「・・・の中から誤っているものはどれか」で答えが「3番」なら、その問題の「3番の設問を黒マーカーで塗りつぶしておく」ということです!
これをやっておけば、残された設問はすべて正しい記述となるのでそれも覚えていきます!

正しい記述の設問は解説と同じです!
誤った記述の設問は消し去っておいて、間違って覚えてしまうことを防ぎます!
ノートは作らず、問題集に直接書き込む
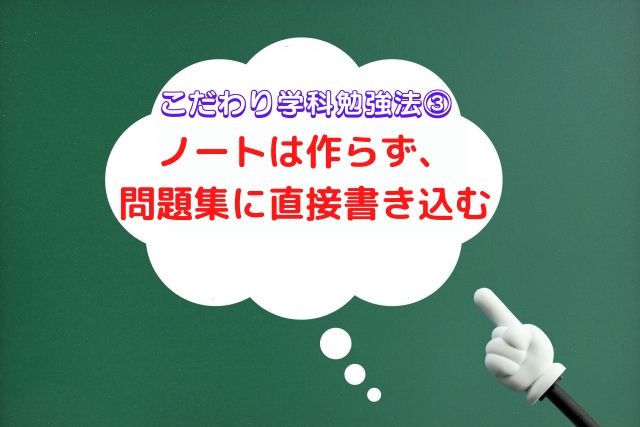
書き留めておきたいことは、問題集に直接書き込みをします!
例えば、
『”以上”や”未満”といった言葉を赤丸で囲む』
『キーワードをマーカーする』
『補足を余白に追記する』
こういったものはすべて問題集にそのまま書き加えます!
そうすれば、一冊の問題集で勉強のすべてをまとめておけます!

一冊にすべてまとめておけば、その一冊だけ持ち歩けばどこでも勉強することができます!
試験当日も、その一冊だけ持っていけば済むので楽ですよ!
1日5分など、無理しない程度に「毎日続ける」
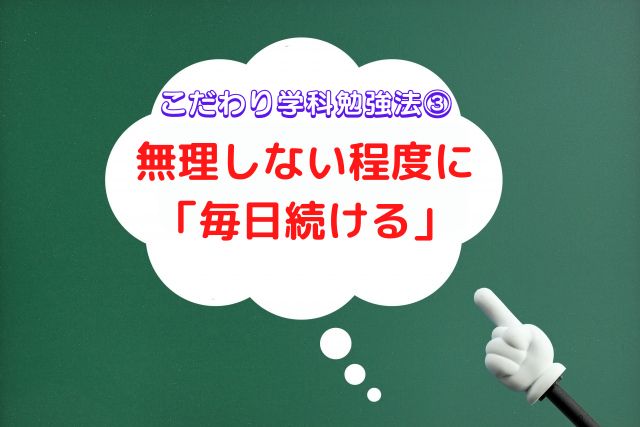
一番効率の良い勉強法は「毎日つづける」これに尽きます!
ただ毎日つづけると言っても、勉強する時間は無理をしません!
人間の集中力は、もって30分と言われています!
1回の勉強時間も多くてそのくらいです!
気分が乗らないときもあるので、そんなときは5分だけやって終わりにしますww
逆に30分を超えるような勉強だと、ただ字ズラだけ追っているだけの無駄な時間になるのでやりません!
「人間の限界は超えない」これが毎日続けていく秘訣だとわたしはおもっています!

毎日ちょっとずつやる方が寝てる間に脳が勝手に整理してくれるので、実は効率がいいんですよ!
私のこだわり「製図」勉強法

わたしは製図試験も独学で突破しました!
とは言え、完全独学というわけではありません。
わたしの会社に過去に2級建築士を取った人がいて、その人に教わった手法を実践して合格を勝ち取ることができました。
その手法はかなり理にかなっていたので、4つのポイントに分けてお話ししておきます!
- 描きやすい道具を揃える
- 描き方の手順を覚える
- 大幅な減点ミスを防ぐ
- 経験者に聞きまくる
描きやすい道具を揃える
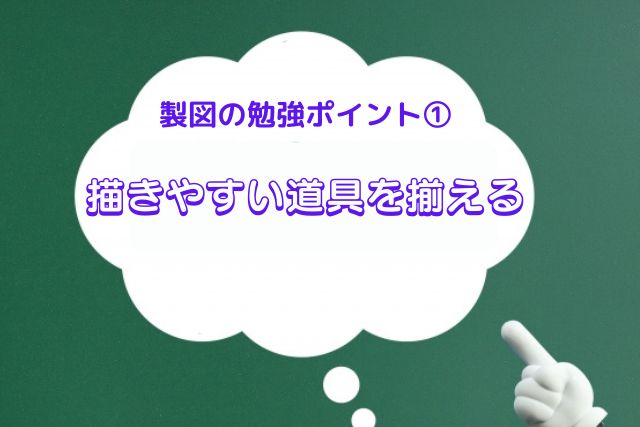
製図の勉強は、製図道具が無いと始まりません!
時間との勝負となる製図試験では、描きやすい道具を揃えることがかなり重要です!
同じ製図道具でも材質・重さ・形状などで作図効率がまったく変わってきます!
自分に合った道具を見つけ出すためにも、早めに道具に触れていくことも大切です!
学科の合格発表を待ってからでは勉強時間が十分に取れなくなるので、学科が終わったらすぐに製図道具は用意するようにします!

おすすめの製図道具について、このブログでも紹介しています!
一級建築士用で紹介していますが、二級建築士でも揃える道具は同じです!
一発合格した私が実際に本試験で使った製図道具を紹介しています!
是非参考にしてみてください!
描き方の手順を覚える
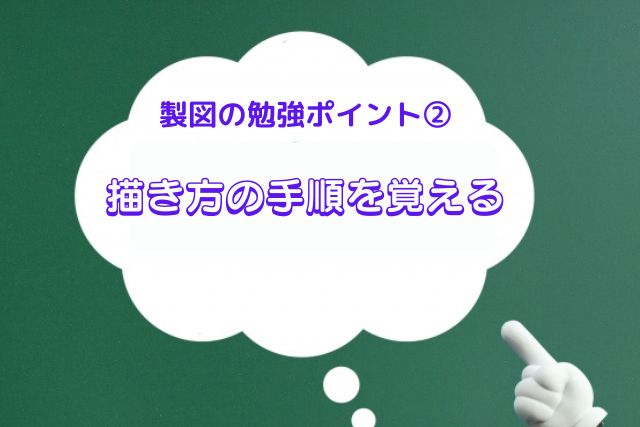
二級建築士の製図試験は、とにかく「描き上げれたヤツが勝つ」と言っても過言ではないです!
だからこそ、図面を描くスピードは超重要です!
図面を素早く描くためには「描き方の手順」をマスターすることが重要です!
平面図で言えば
- 通し柱を描く
- 壁を描く
- 窓・建具を描く・・・
といったように、パーツごとにどの順番で描いていくのかを決める(体に覚えさせる)ことです!
描き方の手順をマスターすれば、図面を描くスピードは格段に速くなります!
描き方手順はテキストでマスターする
描き方の手順を覚えるには、市販のテキストが最適です!
スタンダードな製図テキストなら、総合資格のものが良いでしょう!

まずはお手本通りの手順で描いていき、徐々に自分が描きやすい手順に昇華していくと良いです!
大幅な減点ミスを防ぐ
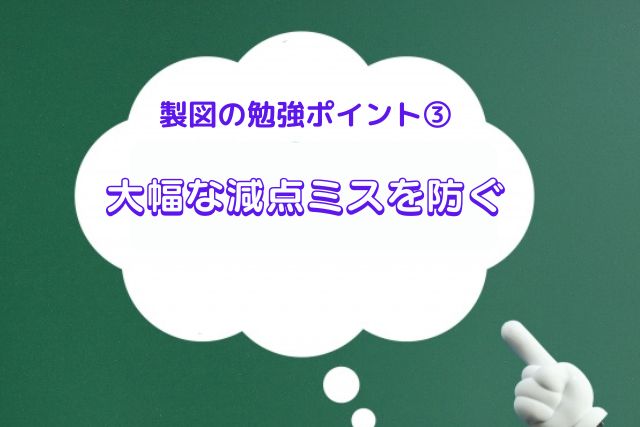
図面を描き上げることと同じくらい大事なのが、大幅な減点ミスをつくらないことです!
木造住宅で言えば、
- 火打梁の描き忘れ
- 通し柱の表示忘れ
- 耐力壁の表示忘れ・・・
といったことです!
こういった構造耐力上重要になってくるものが欠落してしまうと、大幅な減点となってしまいます!
特に木造課題では大幅減点となるポイントがいくつかあるので注意が必要です!
そのポイントについてはここで話すと長くなるので別記事で詳しく書いています!

3階建てや2方向道路のときの『道路斜線』
第一(二)種低層のときの『北側斜線』
こうした法規制についても本番で見落としがちなので注意が必要です!
受験年の演習課題でポイントを掴む
製図課題から想定される重要ポイントをつかむことも、大幅減点を防ぐためには大切です!
課題発表前にやみくもに対策しても無駄な努力となったり、かえって余計な知識がついてしまったりします。
製図課題は学科試験後に発表されます。
そのため、課題発表後(約1ヶ月後)に発売される演習問題を用意しておくと良いです!
受験年に即した課題条件・敷地条件の演習課題をこなしていくことで、身につけておくべき知識や注意するべきところがクリアになっていきます!
おすすめの演習課題集はこちらです!
経験者に聞きまくる
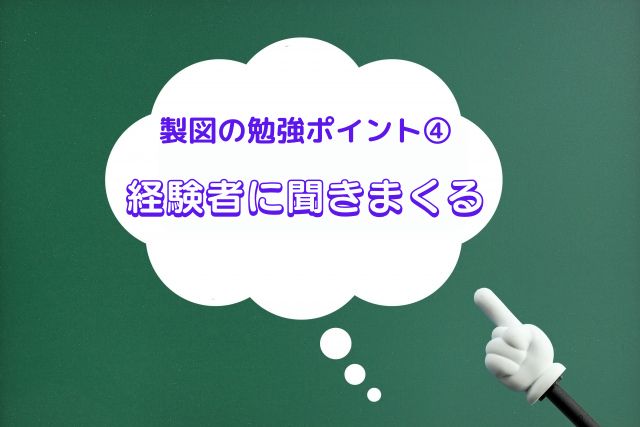
製図試験は、課題条件を素直に守った無難な図面に仕上げることが何より大切です!
独創的で独りよがりな図面は、採点官にアラを探されたり思わぬミスを引き起こすリスクが高くなるため危険です!
無難な図面に仕上げていくためには、自分の描いた図面を客観的に見ることが必要不可欠です!
客観的な視点を取り入れるには、人に聞くのが一番です!
製図試験を合格している人や指導しているような人が身近にいるなら、積極的に活用すべきです!
私は会社にそういう人がいたので、疑問に思ったことや迷ったことについては、どんな些細なことでもすぐに聞くようにしていました!
質問したり図面を見てもらいフィードバックをもらうことで、自分では気づかなかったことが可視化されていき、第三者的な視点も磨かれていきます!

私が当時聞きまくった「どんな課題でも使えそうな無難な図面に仕上げるコツ」について下の記事で紹介しています!
合格しやすい「無難な図面」に仕上げるコツはこちら!
番外編:製図課題が木造なら、矩計図を1パターンとりあえずマスターしておく
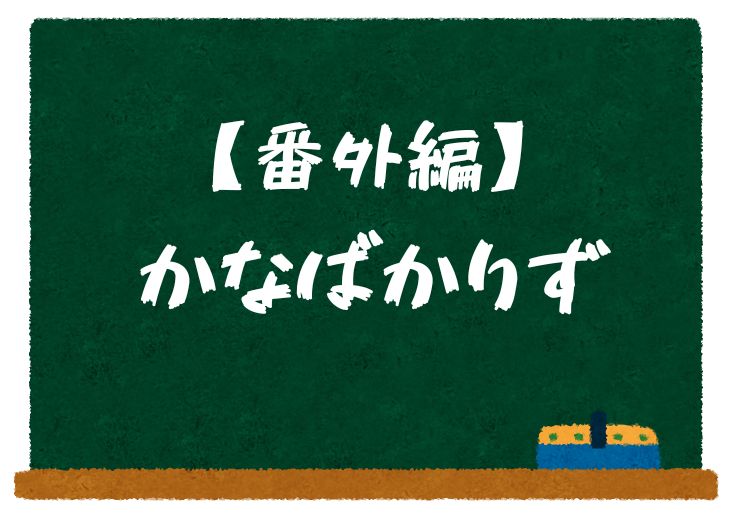
私が受験した当時の製図課題は「二世帯の木造住宅」でした。
そして要求図書の中に矩計図がありました。
当時製図を教えてくれた先輩から
「作図時間を一番取られるのは矩計図。だから矩計図を手早く仕上げるコツを覚える!矩計図が早く描けれるようになれば、あとはなんとかなるよww」
という素晴らしいアドバイスをもらいました!
そしてそのときの指導がとてもユニークだったので紹介します!
矩計図を手早く描き上げるための先輩からの指導がこれです!
- コレと決めた1つの矩図をとりあえず描きまくってマスターする
- 1つマスターして、あとは設問に合わせて数字を変える
- 数字と図面の相違は小幅な減点で済むので、それで逃げ切る
この指導によって、本番のときは他の受験生より早く描き上げることができました!
結果、
最終チェックの時間がしっかり取れて、床伏図に火打梁を描き忘れていることにも気がつけました!
火打梁の書き漏れは大幅減点をくらうので、矩計図で時間短縮できたことが大幅減点を防ぐことにもつながりました!
「損して得取れ」
まさにこれを実践できたような経験でしたww
「独学はちょっとな・・」という人向け!オススメ通信講座
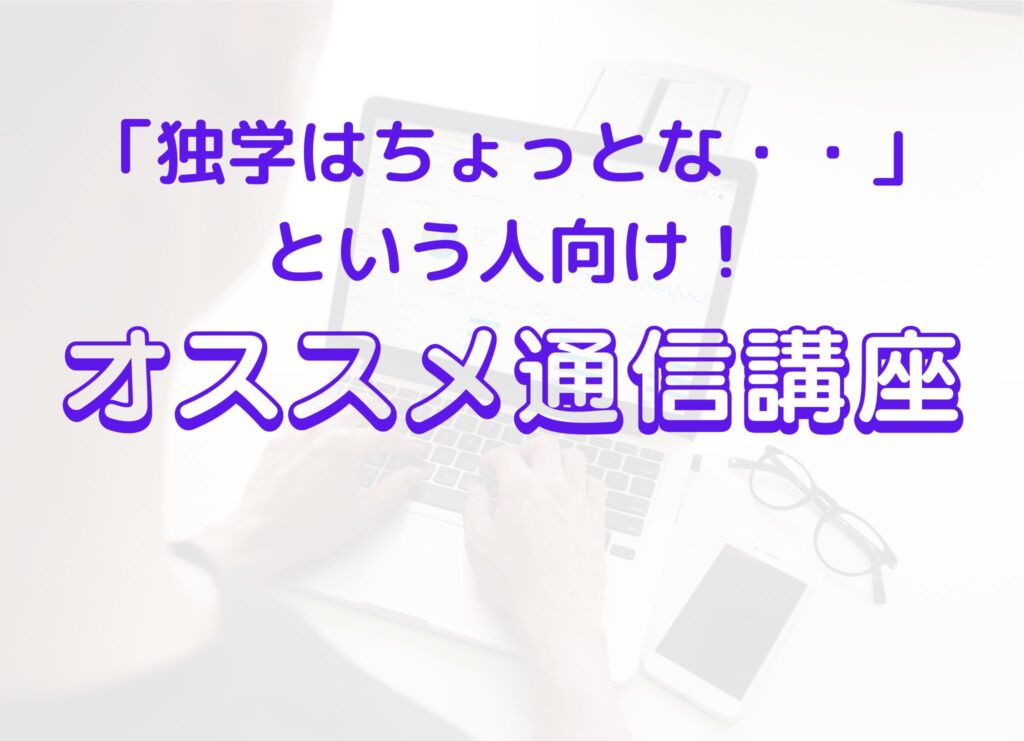
わたしは建築や住宅の予備知識があったり、製図を趣味で教えてくれる先輩がいたことも独学で合格できた要因のひとつかなと感じています。
もし予備知識や身近で教えてくれる人がいなくて「独学はちょっとムリそう・・」とおもっている人には『通信講座』がいいとおもいます!
独学を考えている人に通信講座がおすすめな理由は、次の3つです!
- 教材を探す手間が省ける
- 動画で学べる
- コスパがいい
通信講座の教材は過去問をじっくり研究してつくられていて、テキスト・問題集・講義がそれに連動しています!
市販のものをアレコレ探して追加していくよりも、ひとつのパックになった通信講座のほうが手っ取り早いし手間も省けます!
講義動画をオンライン上でいつでもどこでも見られるので、自分の予定にあわせて好きなタイミングで始められます!
文字だけでは分かりにくいことも動画だと理解しやすくなります!
通勤時間や移動時間にも講義が受けられるので、時間を有効につかえるメリットもあります!
通信講座は運営側も効率化しやすいため、価格がとてもリーズナブルです!
時間を有効につかえて金銭的にも抑えることができる通信講座は、独学からのランクアップとして(時間的にも金銭的にも)コスパがいいです!

ただ、通信講座といっても大手資格学校のものはあまりおすすめしません。
大手学校の通信講座は価格が高く、教材や講義もメイン講座のものを切り取ったようなものだからです。
私のオススメする通信講座は次の3つです!
- スタディング
- ハウジングインテリアカレッジ
- 資格の学校 TAC
それぞれの特徴は次のとおりです!
- 【スタディング】スマホだけで勉強できる
- 【ハウジングインテリアカレッジ】製図に強みがある
- 【資格の学校 TAC】資格学校で最安値
順番にお話ししていきます!
スマホひとつで勉強できる「スタディング」
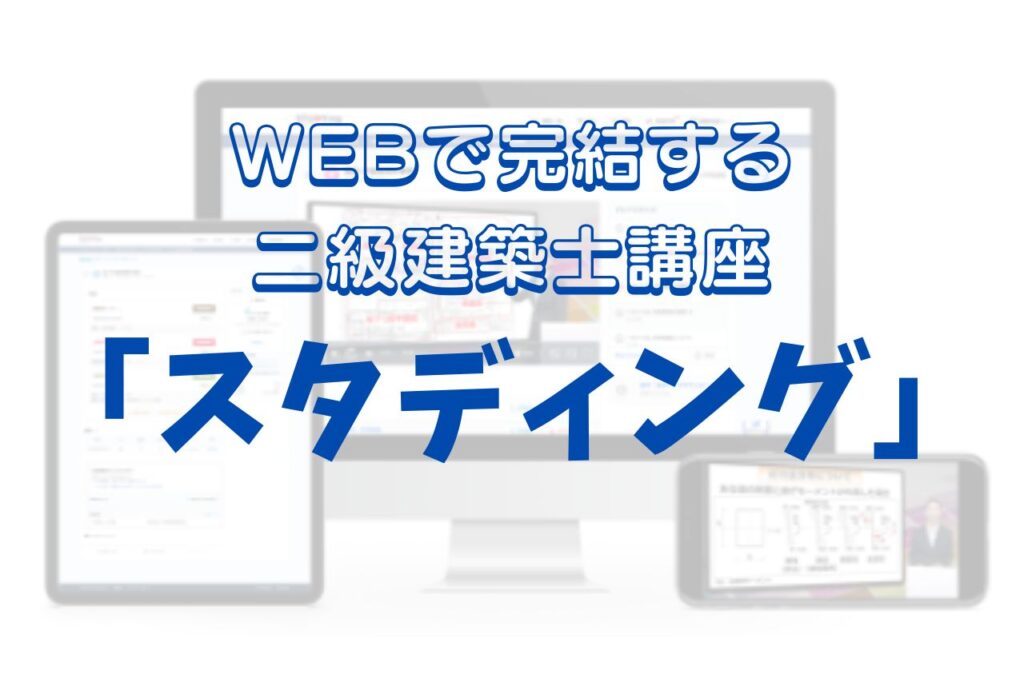
スタディングは私も体験してもっともオススメな通信講座のひとつです!
予定が流動的になりやすい建築業界では、いつでもどこでも勉強できる環境は最強の武器になります!
スタディング二級建築士講座の良さはホントいっぱいありますが、特長として次の3つがあります!
- スマホ学習向けに構成された教材
- 合格することに特化して無駄がない
- 二級建築士講座で最安値級

スタディング二級建築士講座を私も実際に体験しています!
スマホ学習向けに構成された教材
重いテキストを持ち運びせずにスマホで勉強できるとこもいいですが、驚いたのはそのクオリティの高さです!
講義動画はスマホ視聴を前提に作られた資料が使われていて、さながらYouTube動画のように分かりやすいです!
動画だけでも十分勉強できるし、スマホで解く問題集は正誤を記録して再復習もしやすいので苦手克服にとても便利です!
すべての教材を網羅的に探すことができるAI検索機能も優秀で、AIアルゴリズムでGoogle検索のように知りたい情報が上位に表示されるようになっています!
合格することに特化して無駄がない
過去10年分を徹底的に分析していて、頻出問題に絞ってカリキュラム構成がされているため効率よく勉強できるようになっています!
講義動画も1単元が30分程度にまとめられて1セクター5分程度に分かれているので、繰り返しの学習で知識を定着させることにも適しています!
「頻出問題」+「繰り返しの学習」という最小の労力で最大の効果を発揮する学習が可能になります!
激務が多い建築業界において無駄がなく効率よく勉強できるのはかなりの強みと感じてます!
二級建築士講座で最安値級
最安値級の料金もかなり魅力です!
学科・製図セットでこの料金はほかを探しても見つからないとおもいます!
学科・製図 総合コース:88,000円(税込)
資格取得に投じた金額が少なければ、取得後に資格手当や年収アップなどで費用回収する期間も短くなります!
スタディングでは講座の一部を
無料体験することができます!
おすすめなので是非体験してみてください
スタディング二級建築士講座を
私が実際に体験した記事はこちら
製図に強みがある「ハウジングインテリアカレッジ」

二級建築士試験は一級と比べると出題範囲も狭いため、学科は独学でも十分可能です。
ただ、製図試験を完全独学で目指すのはかなりキツイものがあります!
そのため製図だけ通信講座を利用する人も多いです!
製図の通信講座は「ハウジングインテリアカレッジ(略称HIC)」が一番おすすめです!
ハウジングインテリアカレッジは20年以上前から二級建築士の製図試験に特化して指導してきたベテランの資格スクールです!
わたしがハウジングインテリアカレッジをおすすめする理由は、次の4つの特長があるからです!
- 添削課題が6課題と豊富
- いつでも質問できるサポートが充実
- 3ヶ月で合格まで導く学習カリキュラム
- 講座費用が安い

製図攻略のカギは、丁寧な添削指導といつでも質問できるサポート体制を持つことです!
添削課題が6課題と豊富
ハウジングインテリアカレッジは丁寧な添削に定評があり、多数の合格者を輩出してきたことがその裏付けとなっています!
ハウジングインテリアカレッジの添削課題は、合格必勝添削問題(5題)と模擬試験問題(1題)の合計6課題です。
合格必勝添削課題は、毎年6月に発表される設計製図課題に沿ったHICオリジナル課題です!
模擬試験問題は、本試験と同じ時間で解いていき最後にランク判定もしてくれます!
添削課題が少なすぎると不十分ですが多すぎると作業のようになってしまうため、HICの6課題は丁度良いです!
いつでも質問できるサポートが充実
製図の勉強をしていると「これっていいのかな?」「こういう場合ってどうするの?」など、山のように疑問が出てきます!
ハウジングインテリアカレッジでは、通信講座でもメールでいつでも講師に直接質問ができます!
しかも質問回数は無制限です!
講義を見ていてわからなかったときや、課題を解いていて気になったときなど、すぐに質問して解決していけるのはかなり安心です!
3ヶ月で合格まで導く学習カリキュラム
ハウジングインテリアカレッジは、初受験の人が合格まで到達できるように導いていってくれる学習カリキュラムも魅力です!
「基礎力養成期(6~7月)」「合格力アップ期(7月)」「総仕上げ期(8~9月)」の3タームに分けてステップアップしていくカリキュラム構成となっています!
- 基礎力養成期(6~7月)では、エスキスの考え方など基礎的なことを習得します。
- 合格力アップ期(7月)では、敷地条件・法的制限などより実践的なスキルを身につけていきます。
- 総仕上げ期(8~9月)では、今年度課題でのポイント理解を深めて本試験へ向けての総仕上げをしていきます。
課題もこれに合わせて発送時期がずらされているので、それぞれのタームごとにやるべきことをじっくりと学習していくことができます!
講座費用が安い
製図講座の料金が大手と比べてかなり安いこともハウジングインテリアカレッジの魅力のひとつです!
二級建築士講座(製図):108,900円(税込)
比べてみるとその差は歴然です!
| 通信講座 | 費用(税込) | 添削課題 | 質問回数 |
|---|---|---|---|
| ハウジングインテリアカレッジ | 108,900円 | 6課題 | 無制限 |
| 日建学院 | 143,000円 | 3課題 | 質問券利用で可能 |
| 建築士会 | 138,000円 | 10課題 | 無制限 |
| TAC | 143,000円 | 4課題 | 15回 |
また、ハウジングインテリアカレッジの製図講座は教育訓練給付制度が利用可能なので条件に合う人は制度を利用してみると良いでしょう!
公式サイトでは講義動画の一部を無料視聴することができます!
気になる方は公式サイトをチェックしてみてください!
ハウジングインテリアカレッジの「製図講座」については
こちらで詳しく書いています!
2024年から「学科講座」も誕生!
製図に強みのあるハウジングインテリアカレッジから、この度「学科講座」が誕生しました!

実績のある製図講座に学科も加わったことで、二級建築士対策はこれだけで十分じゃないかと思います!
「学科講座」は、以下の3つの特徴があります!
通信講座でも確実に実力を身につけるためのサポート体制も充実しています。
学科+製図セットの料金を、他の講座と比較しながら紹介しておきます。
| 受講料 (学科+製図セット) | 教育訓練給付制度 | 合格祝い金 | 添削課題 | 質問対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジングインテリアカレッジ | 138,900円 | 対象 (27,780円) ※製図分※ | Amazonギフト券5000円 | 6課題 | 無制限 |
| スタディング | 88,000円 | なし | 1万円 | なし (4課題を自己採点) | 1問につき1,500円~1,000円 |
| 日建学院 | 約61万円 | 対象 (約9万) ※学科分※ | なし | 3課題 | 質問券利用で可能 |
| TAC | 約34万円 | 対象 (約4万円) ※学科分※ | なし | 4課題 | 15回 |
| 建築士会 | 約15万円 | なし | なし | 10課題 | 無制限 |
添削課題や質問対応などのサポート面も含めて考えると、かなりコスパの良い総合講座になります!
製図の強みに学科講座も加わったことで
まさに『最強の二級建築士講座』になりました!
ハウジングインテリアカレッジの「学科講座」については
こちらで詳しく書いています!
資格学校で勉強したいなら「資格の学校 TAC」
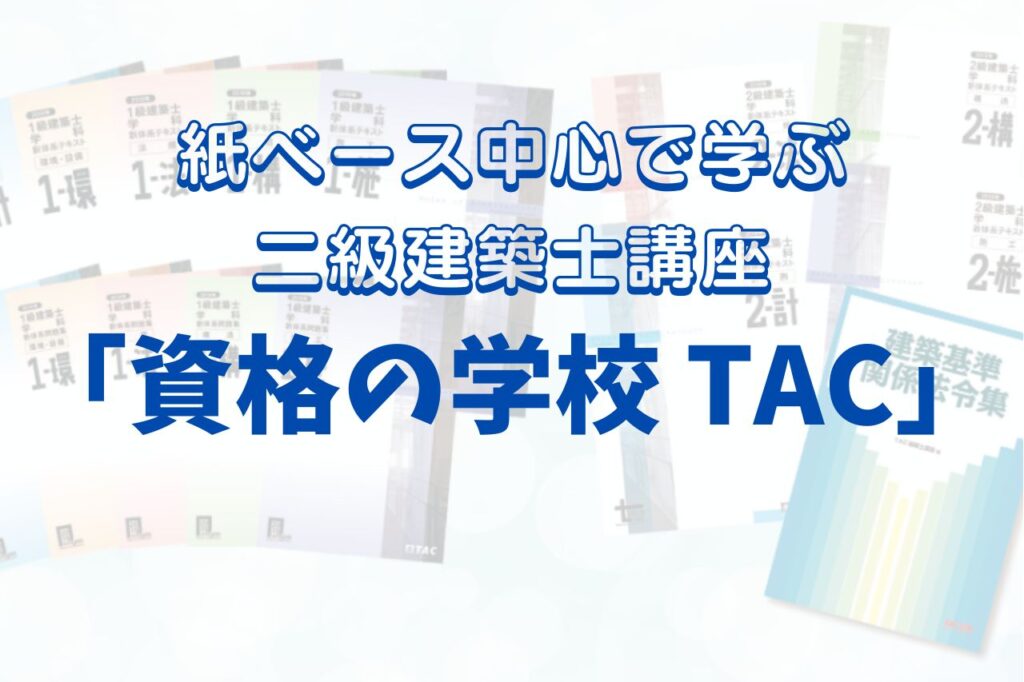
「紙のテキストで覚えたい」「問題集は紙がいい」という人もいるとおもいます!
そんな人には、TACの二級建築士講座がおすすめです!
- 紙の教材が豊富にある
- 質問や添削で疑問点を解決できる
- 大手と比べて価格がリーズナブル
学科講座は約20万円ほど、製図講座も15万円ほどと、SやNに比べてリーズナブルな価格設定です!
わたしの感覚ですけど、二級建築士講座としてSやNは高すぎる気がしますww
むしろTACの価格設定のほうが妥当な気がします!
- 学科本科生:198,000円(税込)
- 製図本科生:143,000円(税込)
TACは通学だけでなく通信講座もあります!
通信講座でも通学と同じ教材で学ぶことができますし、質問や添削のサポートもあります!
近道せずに正攻法で試験に臨みたい人にTACはおすすめです!
TACのことはこちらで詳しく書いています
二級建築士で求められる知識レベル

二級建築士の試験問題の根底になるのが「二級建築士が建築できる範囲の知識があるか」を問うものです!
二級建築士が建築できる範囲
二級建築士が建築できる範囲は、
- すべての構造で、高さ13m以下 かつ 軒高9m以下
- 木造は、500㎡以下
- 木造の”一般”建築物の場合、1,000㎡以下まで可能
(木造の平屋の”一般”建築物なら、無制限) - 木造の”特定”建築物の場合、同じ500㎡以下まで
- 木造以外(RC造など)は、300㎡以下
- 木造以外(RC造など)の場合、”一般”建築物でも”特定”建築物でも、同じ300㎡以下まで
ざっくり言うとこんな感じです!
ちなみに
”特定”建築物とは、学校・病院・劇場・百貨店といった不特定多数の人が利用する公共性の高い建築物のことです!
”一般”建築物とは、”特定”建築物以外のことです!
建築できる範囲から「求められる知識レベル」が分かる
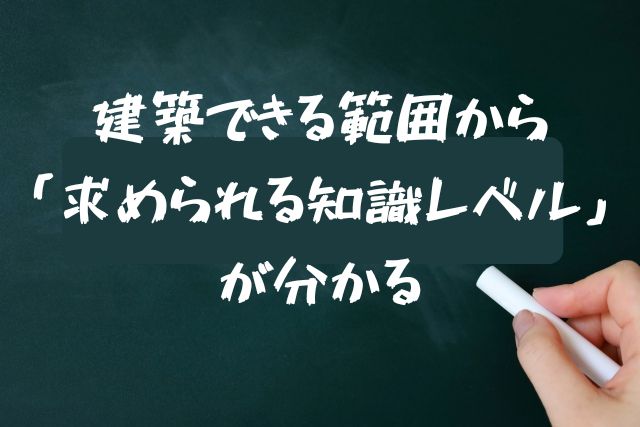
- 3階建てがMAX
- 建売住宅3~5軒分程度の広さがMAX
- 木造の”一般”建築物なら大規模にできる
高さ13m以下かつ軒高9m以下は、階数で言えば3階建てがMAXということです!
木造の500㎡以下は、坪数で言えば約150坪以下の広さです!
木造以外(RC造など)の300㎡以下は、約90坪以下の広さです!
一般的な建売住宅が30坪程度の広さなので、建売住宅3~5軒分くらいの広さということです!
もっと広い建物をつくりたいなら、木造の”一般”建築物にするしかないです!
こう見ると、二級建築士が建てれるサイズ感ってけっこう一般的ですよね!
木造の”一般”建築物なら広くつくれますが、それでも用途は一般的なものです!
つまり、
二級建築士の試験では、この一般的な建物を建築するための知識があるかどうかが問われてきます!
二級建築士試験では
「建築に関する一般的な知識」
が問われる
二級建築士の勉強時間は?
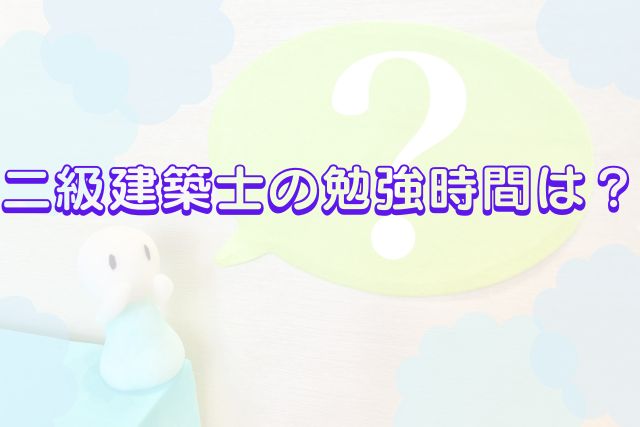
二級建築士に必要な勉強時間は次のように言われています!
- 建築の予備知識あり:500時間程度
- 建築の予備知識なし:1000時間程度
建築の予備知識ある人が学科試験6ヵ月前の1月から勉強開始した場合、単純計算で1日3時間程度の勉強時間となります。
予備知識ない人はその倍になるので、およそ1年前から1日3時間の勉強時間となります。
ただ、
これはあくまで一般論であって、勉強のやり方によって大きく変わるとおもいます!
わたしはなんでも効率化したがる性格なので「無駄なことは一切しない」を徹底して一般論より短い勉強時間で合格しました!
つまり勉強時間はあくまで結果論なので、それよりも勉強のやり方の方が重要だとおもいます!
二級建築士の勉強スケジュール
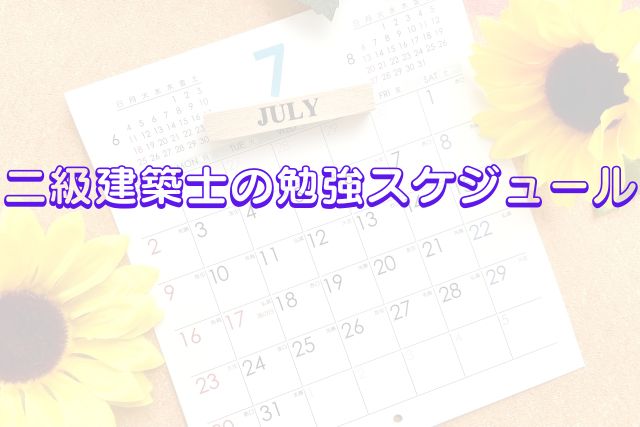
勉強スケジュールを組み立てるためには、まずは学科・製図の試験日がいつなのかを把握する必要があります。
二級建築士の試験日は例年、次の日程となります。
| 【試験種別】 | 【試験日】 |
|---|---|
| 学科試験 | 7月の第1日曜日 |
| 製図試験 | 9月の第2日曜日 |
試験日程からも分かるように、学科の勉強は遅くても6月末までに、製図の勉強は9月初旬までに、それぞれ終わらせておく必要があります。
初受験の人のスケジュール
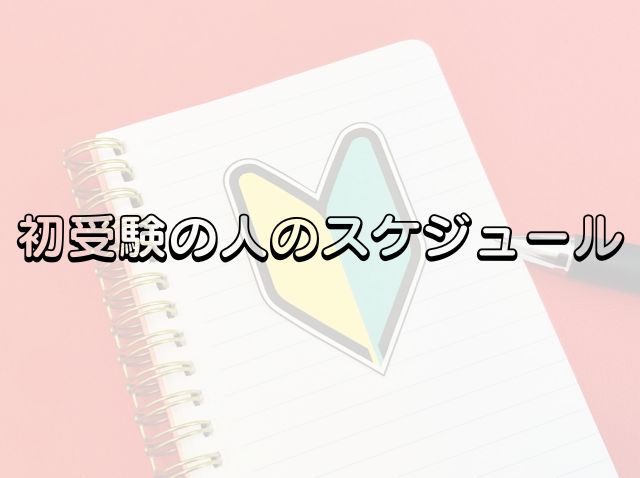
建築の予備知識がない人の場合、先述したように勉強時間はおおむね1000時間程度となります。
1日3時間程度を勉強に当てられるとして6月末までに学科の勉強を終わらせるには、学科試験のおよそ1年前からスタートすると良いでしょう。
一方、
建築の予備知識がある人の場合はおおむね500時間程度の勉強時間となるため、学科試験のおよそ6ヶ月前(受験年の1月)から勉強スタートさせれば良いでしょう。
製図試験は学科試験の約2ヶ月後にあります。
製図試験の約3ヶ月前(学科試験の少し前)から製図の勉強を少しずつ始めるのが理想的と言われていますが、学科試験を終えてから勉強を始めても十分間に合います。
私もそうですが例年ストレート合格する人は十分いますので、焦らずまずは学科試験の勉強に集中しましょう。
製図から受験する人(学科合格している人)のスケジュール
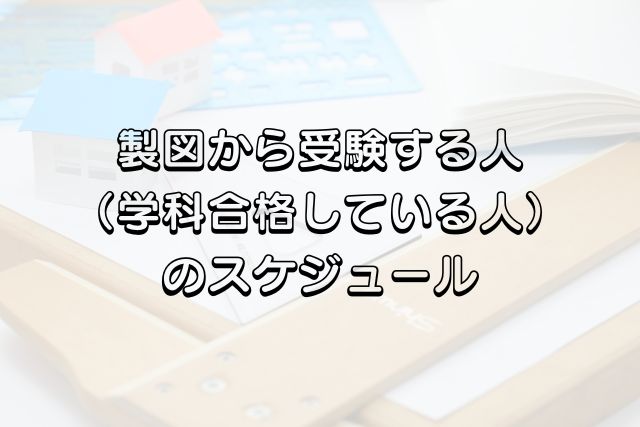
二級建築士の製図試験は、学科合格したその年を含めて5年以内に3回までチャレンジすることができます。
そのため製図から受験する人もいると思います。
その人は製図課題の発表(製図試験日の約3ヵ月前)から勉強をスタートさせると良いでしょう。
二級建築士の製図課題は「木造→木造→RC造」といったように、2年続けて木造の後にRC造となるのが通例と言われていますが、本当にそうなるかどうかは課題が発表されるまでは分かりません。
決め打ちしてヘタな知識を付けないためにも、課題発表を待ってから本格スタートするのが得策と思います。
もし課題発表前から勉強を始めるのであれば、製図道具に慣れる練習や1年経過して忘れかけてる学科を復習するなど、課題発表までは基礎を固めることに時間を使うと良いでしょう。
まとめ
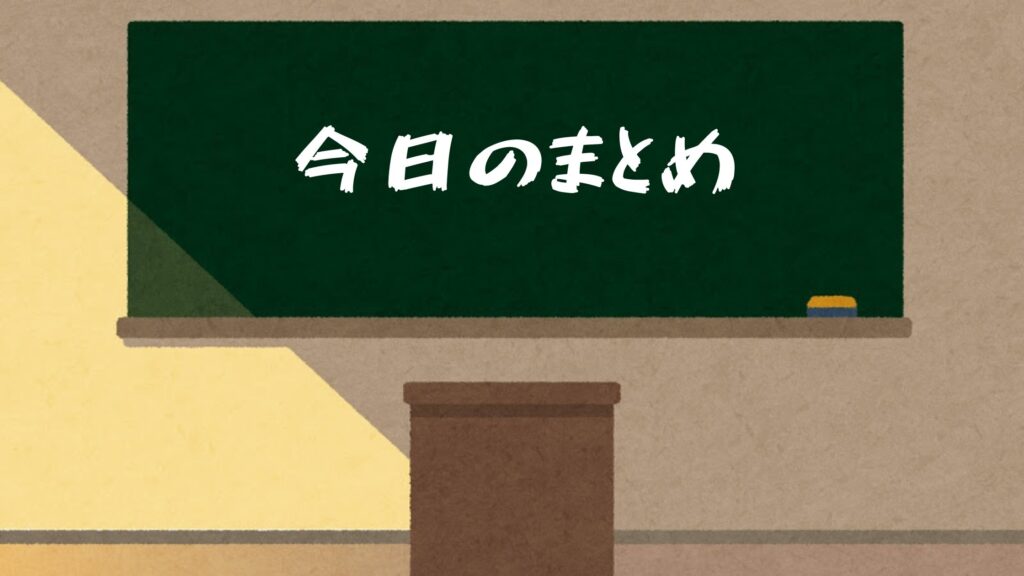
今日はわたしが実際にやっていた「二級建築士の独学勉強法」についてお話ししてきました!
二級建築士は独学で十分狙える資格です!
私がそう考える理由は次の2つです!
- 学科でよく出る問題はだいたい決まっている
- 製図は描き上げる力があればたいてい受かる
学科は建築に関する一般的な知識を問われるので、建築学科卒などそれなりに予備知識がある人には十分独学で挑戦可能です!
わたしの学科勉強法は次の4つです!
- 問題は解かずに、解説だけ読む
- 正しい設問だけ残して、それも覚える
- ノートは作らず、問題集に直接書き込む
- 1日5分など、無理しない程度に「毎日続ける」
製図はミスをせず描き上げる力が求められます!
わたしは次の3つを重要ポイントとしました!
- 描きやすい道具を揃える
- 描き方の手順を覚える
- 大幅な減点ミスを防ぐ
ここまで独学の勉強法を紹介してきましたが、
わたしは建築学科卒で仕事も住宅関係なのでそれなりに予備知識がありました。
製図も身近に教えてくれるやさしい先輩がいたのも独学で合格できた大きな要因でした。
建築の予備知識が無くて不安な人は、スタディングなど学科から通信講座を利用することをおすすめします!
また、製図試験の完全独学はかなりキツイので、身近に教えてくれる人がいない人はハウジングインテリアカレッジの製図講座がおすすめです!
あなたにとって最適な勉強法がこの記事をきっかけに見つかってもらえるとうれしいです!
応援してます!
がんばってください!
最後までお読みいただきありがとうございます!
もしこのブログが
「参考になった」
「わかりやすかった」
とおもっていただけたら、
SNSなどでシェアしていただけると
大変うれしいです!
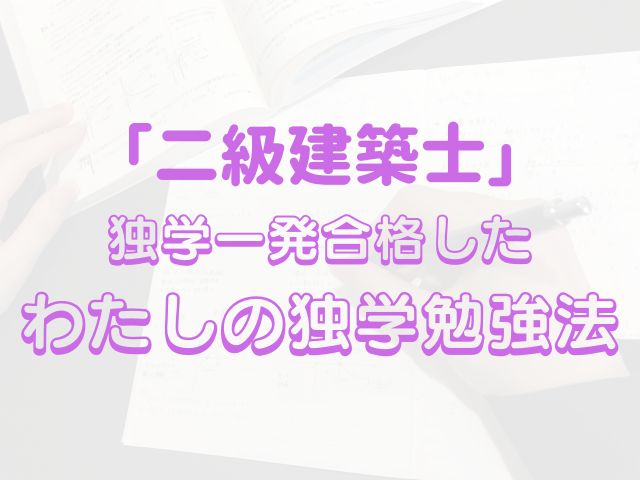
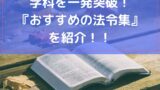
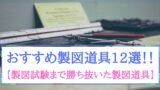
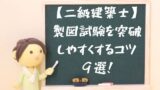
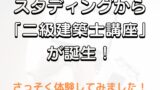

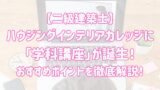

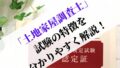
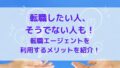
コメント