こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
今日のテーマは
製図の勉強はいつから始めるのがベストか?

学科終わったけど製図の勉強っていつからやるの?

学科の合否判定出てから始めるの?
学科試験の結果が分かるまで時間がかかるため、製図対策に入るタイミングを迷う人も多いとおもいます!
学科の合否判定は製図試験の約1ヶ月前なので、そこから製図対策に入っては遅すぎます!
それではいつから勉強開始すれば良いのか?
それは、、、
学科試験の直後から!
これが結論です!
学科試験が終わったら合否を待たずにスタートすることがベスト!
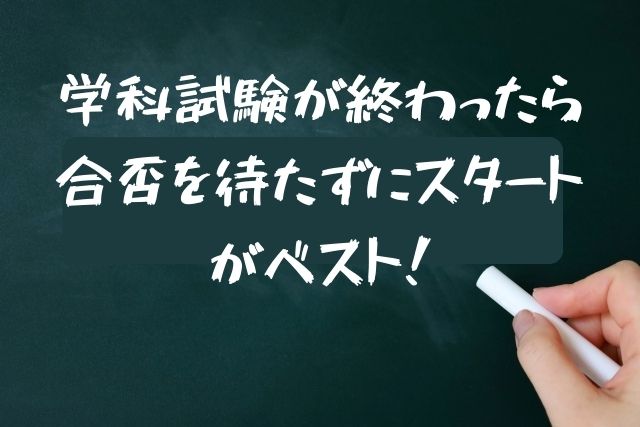
学科試験が終わったらすぐに製図対策に入ることをおすすめします!
理由は「学科の知識がまだ残っているから」です!
図面を描くにしても学科の知識は必要です!
要点記述については特に重要になってきます!
せっかく勉強して得た知識が風化してしまわないように、すぐに製図対策に乗り出すようにしましょう!
それに、
製図試験は相対評価で合否が決まります!
まわりの受験生より開始が遅れるとそれだけ不利になってしまいます!
大手資格学校では、学科試験終了したその日から製図対策に乗り出してきます!
ライバルたちに差を開けられないように、間髪入れずに動き出す行動力が大切です!
学科の手応えが微妙でもあきらめない!
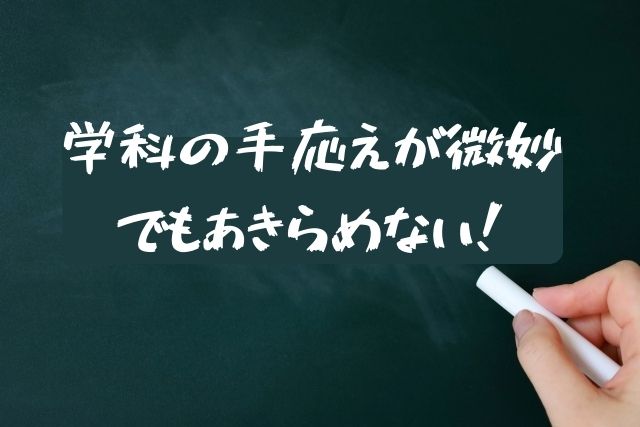
たとえ学科試験の結果が納得のいくものでなかったとしても、最後まであきらめてはいけません!
合格基準点は、受験生全体の出来不出来に左右されため下がる可能性も十分にあります!
わたしが資格学校に通っていたときに「どうせ学科は落ちた」と思っていた人が実は学科合格して慌てて製図試験勉強を始めた人がいました!
このブログを読んでいただいている人にはそうなってほしくありません!
ですから、
学科試験の合格発表があるまでは、とりあえず製図試験の勉強をスタートしておくことをおすすめします!
製図を次の年にまわすのはリスクでしかない
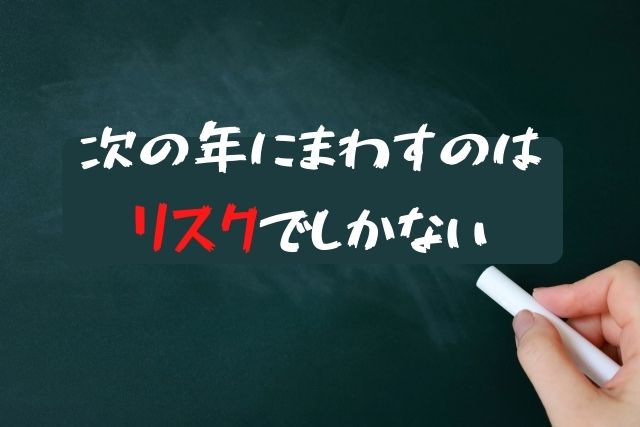

学科から製図まで時間無いから来年にしようかな・・・

今年の課題はムズカシそうだからパスしようかな・・・
製図試験は学科試験合格後に3回チャレンジできるので、こんな誘惑にかられる人もいるかも知れません。
しかし、
この先延ばしする考えはリスクでしかありません!
その理由は、学科の知識が風化しきってしまうためです!
せっかく勉強して覚えた知識も、1年も経てばキレイさっぱり忘れてしまうというのが人情ですww
また一から覚えなおすのは最初に覚えるときよりも大変です!
余計な労力と時間がかかるので避けたほうがいいです!
それに、
たとえ課題が難しかったとしてもそれは他の受験者も同じことです!
相対評価で見られる製図試験では、むしろ課題が簡単なときほど難しくなる(減点項目をより細かく見られる)可能性が高いです!
課題を選り好みするよりもとりあえず突進していく方が、合格できる確率は高くなります!
初年度と過年度では採点官の見られ方が違うと言われている
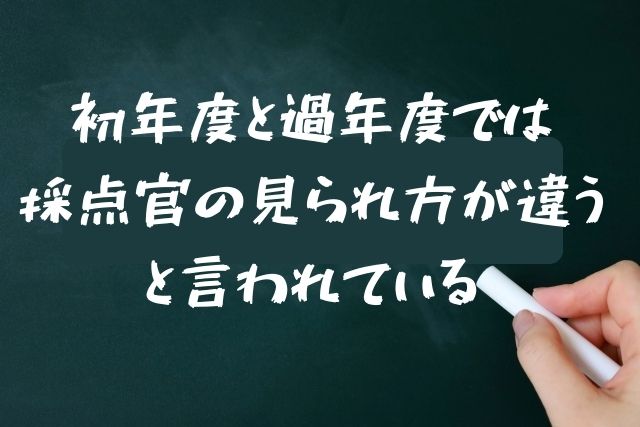
学科試験合格の年に製図まで受ける人のことを「初年度受験生」といいます。
製図2回目など学科合格年以降に受ける人のことを「過年度受験生」といいます。
過年度の人の図面は初年度の人より採点官にじっくり見られると一般的に言われています!
受験番号もしっかり分かれています!
(わたしが受験したときも初年度の私と過年度の知人の受験番号はケタが違うほど飛んでいました)
初年度と過年度で採点基準が違う可能性は十分にあります!
製図対策に使える時間が初年度の人より長いので、図面のキレイさや描込み量なんかまでしっかり採点官に見られる可能性があります。
じっくり見られるとちょっとした粗まで発見されてしまうリスクが伴います。
製図試験合格に向けては、初年度で勢いよく飛び込んでいく方が有利だとおもいます!
製図試験までの勉強スケジュール
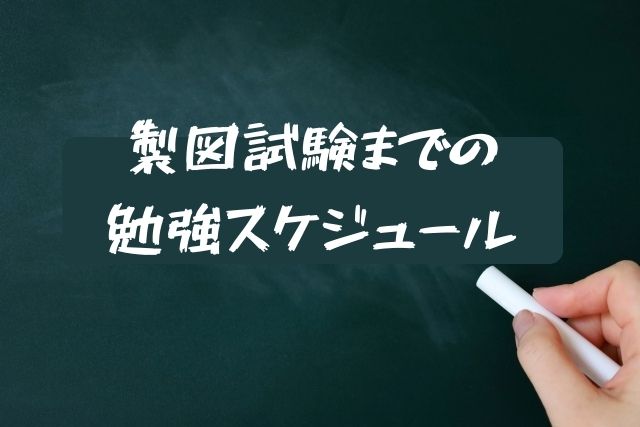
ここからは製図試験までのおおまかな勉強スケジュールについてお話ししていきます!
あくまで「私だったら」という視点なので、まったく一緒である必要はありません!
これからスケジュール組み立てするときの参考にしていただけたら嬉しいです!
学科翌日から取りかかること
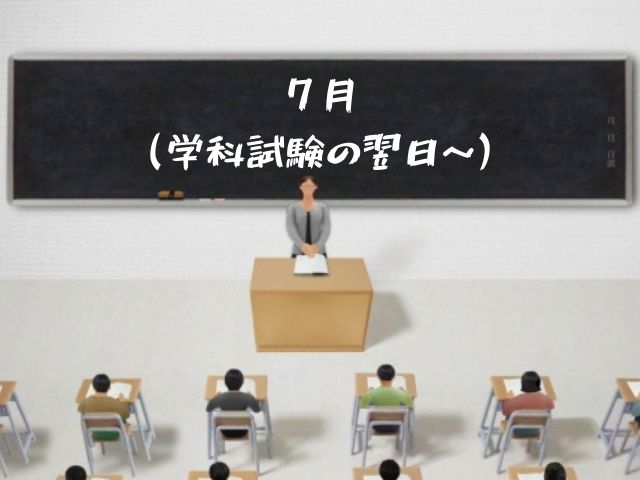
「どういう出題のされ方をするのか?」
「試験時間はどのくらいか?」
「問題用紙はどんな構成か?」
こういった概要を掴むことから製図試験の勉強はスタートします!
まずは相手を知ることが勝負のはじまりです!
相手のことを知らないと戦略はつくれませんからね!
製図試験とはどんなものかについて書いています!
一級向けの記事ですが二級でも考え方は共通です!
やってはダメなポイントを把握する
製図試験にはやってはダメなポイントがあります!
いわゆる一発アウトになることです!
「一発アウトになるものは何か?」こういう重要なものを早めに意識しておくことで、重大ミスを防ぐマインドが定着していきます!
一発アウトの記事はこちら!
やってはダメなポイントを把握する【二級建築士 木造編】
「描き上げることができたら大半は受かる」のように言われている二級建築士の製図試験でも、大幅減点を避けることは大切です!
特に
木造住宅は作図量が多いうえに構造上必要な表記も多いので、重要ポイントを見過ごしてしまうリスクがあります!
たとえ描いているときに見過ごしたとしても、重要ポイントが頭に焼き付いていれば、最後の見返しの時にリカバリーすることができます!
大幅減点ポイントを見抜ければ、合格できる確率は一気に高まります!
木造住宅課題での大幅減点ポイントはこちら!
製図道具はすぐにそろえる

製図の勉強では製図道具が無いと話になりません!
製図試験は図面をどのくらい描いてきたかが本番にとても影響します!
注文して届くまでに時間がかかったり文具屋に買いに行ったら在庫切れだったりすることもあるので、早めに動きましょう!
早めに道具に触れ合っておくことで、自分馴染みの道具に仕上げていくこともできます!
とにかく製図道具は大切な相棒なので、なるべく早く出会えるようにしましょう!
私が実際に製図試験でつかっていた
おすすめ製図道具はこちら!
製図講座に申込
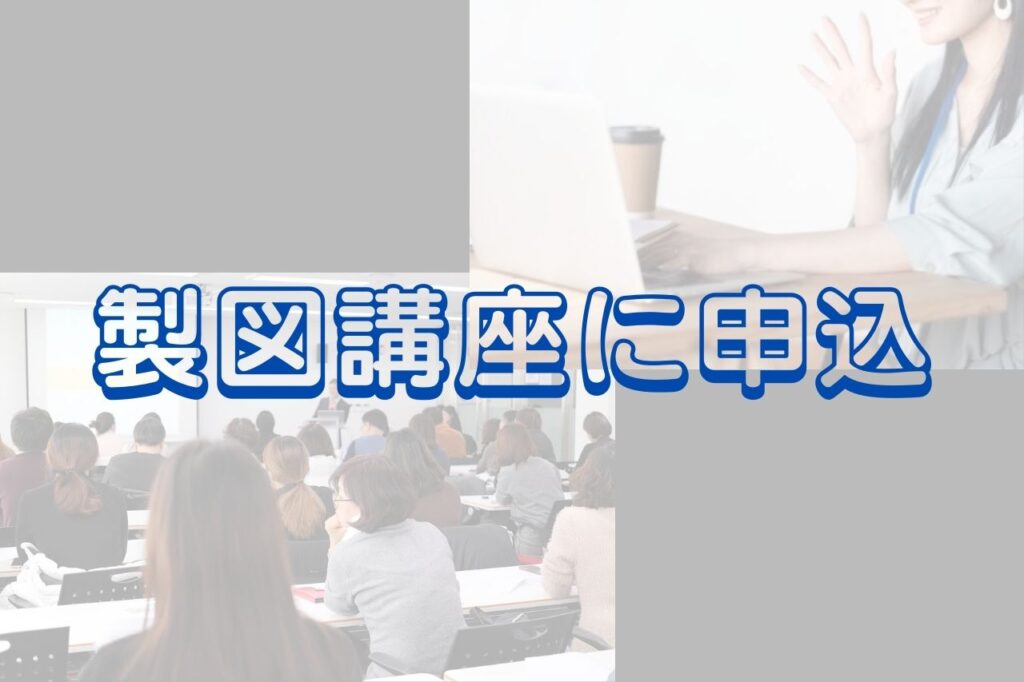
学科試験は独学でなんとかなったりしますが、製図試験の完全独学はかなりキツイです!
製図試験は「他の受験生も描きそうな無難な図面」に仕上げることが合格への最短距離になるので、そのためにも製図試験を熟知した人からの指導はとても重要です!
先述したように初年度で合格できないとリスクが高まるので、ここはケチらずしっかりと対策した方がいいです!
「一級建築士」におすすめ製図講座
私としては、一級建築士ならTACがおすすめです!
- 価格が安い
- 通信講座でも通学並みの授業を受けられる
- 課題の量がちょうど良い(8課題)
- 質問・添削をしてもらえる
TACは「合格者が増えている」「演習課題が面白い」と評価が高いです!
わたしが受験したH29年度のときにも「前の年(H28年度)にTACが本番の製図課題を的中させた」という話を聞き、演習課題の精度はかなり高いとおもいます!
TACについてはこちらで詳しく解説しています!
「二級建築士」におすすめ製図講座
私としては、二級建築士ならハウジングインテリアカレッジがおすすめです!
- 添削課題が6課題と豊富
- いつでも質問できるサポートが充実
- 講座費用が安い
- 3ヶ月で合格まで導く学習カリキュラム
HICは1993年から二級建築士の養成講座を行っている、歴史の長い資格スクールです!
製図試験対策に特化していて、添削・指導への評判がとても良いです!
それでいて価格は大手よりかなりリーズナブルです!
ハウジングインテリアカレッジについては
こちらで詳しく解説しています!
最初はとにかく「作図」に注力する
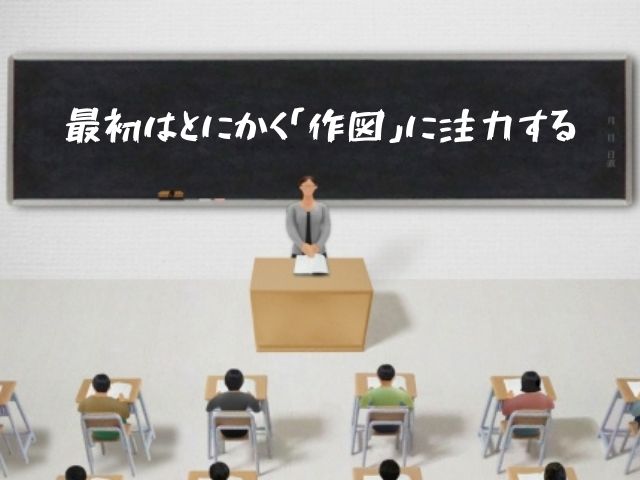
作図時間は、製図試験のなかでかなりのボリュームを取られます!
作図時間は、描けば描いただけ早くなります!
作図時間を短縮することができれば、問題文の読み取りやエスキス・要点記述などにゆとりを生むことができます!
- 描き方の手順をマスターする
- フリーハンドの練習
- 階段や便所など、部位だけをひたすら描く
- 断面図だけをとにかく描く
など、とりあえず描きまくることが大事です!
8月にはお盆休みなど比較的長期の休みもあるので、集中して取り組みます!
もともと作図時間に10時間もかかっていた私が
やってきた作図時間短縮法も参考にしてみてください!
作図に関係することも同時に強化していく
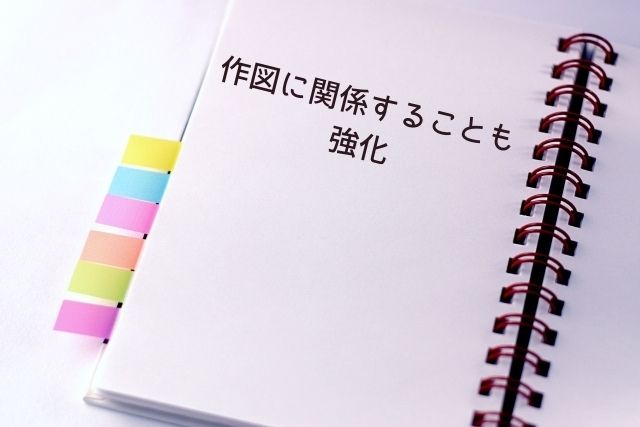
作図だけに注力していると肝心なものを見失うリスクがあります!
ひたすら描くことに慣れていくことと並行して、作図以外のことも強化していきます!
- 見落としをしない問題文の読み取り
- 法的制限にひっかからない
- 要求室の”適宜”に翻弄されない
これらも製図試験では重要です!
このポイントも8月中になるべくおさえていけるようにします!
見落としをしない問題文の読み取り方はこちら!
法的制限にひっかからない対策としてこちらも参考に!
一級建築士の要求室面積でよく登場する”適宜”
「適宜ってどのくらいよ?」と思ったらこちら!
試験1ヶ月前から「記述」もトレーニング
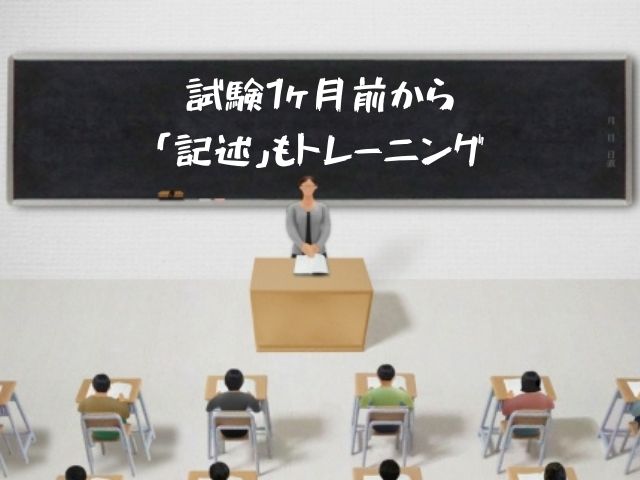
作図に慣れてきた試験1ヶ月前からは、『計画の要点』などの記述のトレーニングもおこなってきます!
「自分なりの記述のテンプレート」を持っておけば、記述にかかる時間短縮につながります!
記述対策は、レパートリーを増やすことに重点をおいてトレーニングしていきます!
『計画の要点』の参考例はこちら!
『補足』も大事!
図面に書く『補足』もレパートリーを増やしていきます!
補足をいっぱい書けるようになると、図面のアピールがしやすくなります!
余白も埋まるので、補足をいっぱい書けるようにしておくと得です!!
『補足』の参考例はこちら!
あとはひたすら課題をこなして、トータルの時間が試験時間内に納まるようにトレーニングしていきます!
製図試験本番を迎える!
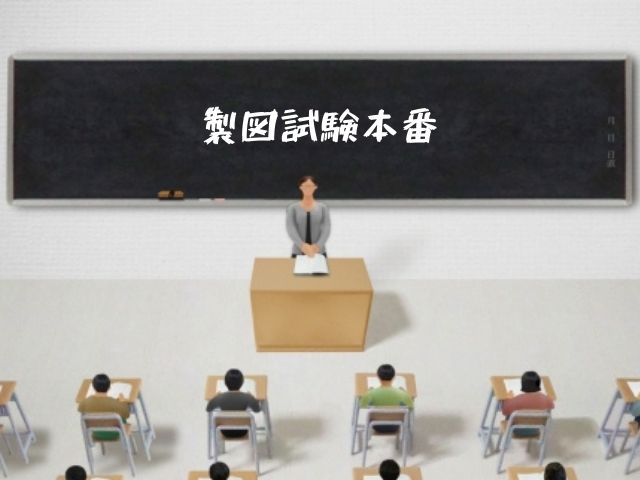
いよいよ製図試験本番です!
これまで蓄えてきた力を思う存分発揮して試験に臨みます!
ただ、試験に向けて頑張ってきた人ほど不安が大きくなるものです。
不安はパフォーマンスを著しく低下させるので、そんなものはサッサと排除します!
そのためには・・・
根拠のない自信をもつこと!!!
私が合格できた実体験でもあり、本当にオススメな手法です!
不安におもってる時点で受かる実力が十分にあるという証拠でもあります!
試験をたのしむ気持ちで、おもいっきりぶつかっていきましょう!!!
根拠のない自信がわたしにもたらした
奇跡について書いていますww
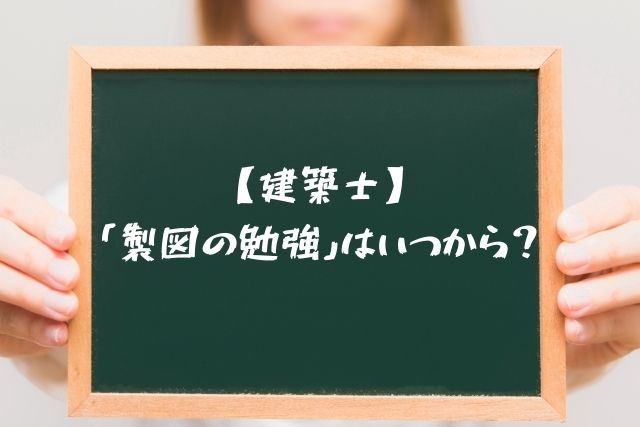
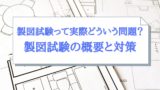
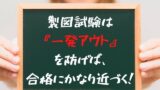
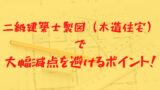
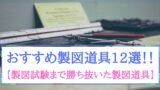
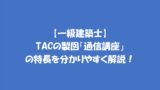

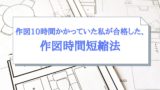
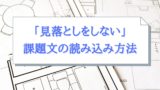


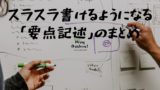
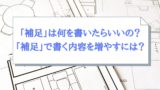


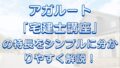
コメント